
TOEICの勉強をしなければいけないけど、モチベーションが上がらない、勉強が続かない。
そんなお悩みはありませんか?
継続が大事だということは分かっているのに、続かない。やる気が出ない。すぐにやめてしまう。
もちろん私も経験があります。
「継続は力なり」と、口で言うのは簡単ですけど、実行するのは難しいんですよね。
このページでは、モチベーションの低下で悩む人のために勉強が続かない時の対処法をご紹介します。
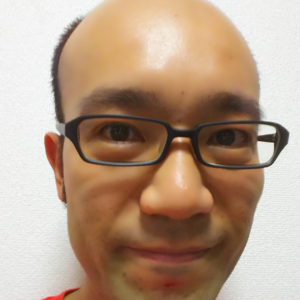 よだ
よだ 英語力を上げるために継続は必須です!
TOEICの勉強が続かないのはなぜ?
最初にTOEICの勉強が続かない理由について簡単にご説明いたします。
続かない理由が分かれば続けるための対処法も見えてきますからね。
そもそも何かを続けることは大変
大前提の話になりますが、TOEICの勉強に限らず「そもそも何かを続けることは大変」ということを知っておきましょう。
何か新しいことを始めた時、最初のうちは新しい発見や学びがあり刺激的で楽しい時間が続きますが、しばらくすると慣れてきて刺激が減っていきます。
常に周囲の環境が変わる状況では、新しい刺激も生まれやすくなりますが、なかなかそのような状況には巡り会えません。
どうしても同じような毎日が続きがち。
そんな中で常に新鮮な気持ちで何かを続けるというのは簡単ではありません。
これはTOEICの勉強に限らず、あらゆることに当てはまる人間の脳の習性です。
ですから、勉強が続かないのも、いわば当たり前。
自分だけができていないのでは?と心配する必要はありません。
続けるのが大変なのは、みんな同じだから大丈夫です。
まずはこのことを頭に入れておいてください。
TOEICの勉強を続けるのは学習内容と同じくらい大変
TOEICの勉強をしている人の悩みは「勉強法が分からない」「内容が難しい」など、いろいろありますが「勉強が続かない」というのも多くの人が抱える悩みです。
勉強する内容が難しいのと同じくらい、勉強を続けることが難しいという人も少なくありません。
英語の勉強は地道に積み上げていくしかありませんが、勉強の成果が出るのに時間がかかるので、そこまで続けるのが大変なのです。
そして、続けることが難しいのは、以下のようにTOEIC特有の理由もあります。
回答がマーク式だから単調になる
TOEICはすべてマーク式で選択肢の中から正解を選ぶものなので、自分で書いたり話したりする形式の試験に比べ、単調になってしまいます。
単調な勉強はどうしても飽きやすくなり、続けるのは大変です。
ですので、たまには選択肢を隠して自分で答えを書いてみるのもいいと思います。
TOEICのように与えられた選択肢の中から選ぶのではなく、何も書いていない所に自分で答えを書くというのは、普段と違った頭の使い方が必要になるので、単調さが軽減されます。
何回でも受けられるから気がゆるんでしまう
年に何回も受けられるのはTOEICのメリットと言えますが、それがデメリットとなることがあります。
「もし今回ダメでも、その次頑張ればいいや」と気がゆるむと、モチベーションも低下してしまいますからね。
こればかりは気持ちの問題なので、今回が最後と決めて受験するしかありません。
初心者は特に大変
TOEICの学習を続けるのは多くの受験生にとって大変なことですが、初心者の方にとっては特に大変です。
なぜなら、TOEICの勉強をしてきた経験がないからです。
人間の脳は、慣れていないことをする時に拒絶反応を起こします。
慣れていないことをしたら自分の身に危険が及ぶかもしれないという本能が働くため、できるだけ避けようとするのです。
まだ勉強を始めたばかりの人は、この拒絶反応が強く働き、勉強が習慣化する前にやめてしまうケースがあります。
もちろん、TOEIC学習という新しいチャレンジに刺激を感じることができれば、勉強を続けることもできますが、その刺激も次第に減ってきます。
そうなると、最初は頑張っていたのに、いつの間にかペースダウンし、気がついたら勉強時間がゼロに、ということにもなりかねません。
一番大変なのは独学で続けること
TOEICの受験生はさまざまな環境の中で勉強されていると思いますが、やはり最も大変なのは独学で続けることではないでしょうか。
独学だと、誰かに強制されているわけではないので、そのような環境ではつい自分に甘くなってしまいます。
就活や転職などに必要だからという理由はあっても、毎日の勉強自体を強制されるわけではありません。
一緒に勉強している人がいれば、それが自分のモチベーションにもなりますが、独学で勉強を強制されない環境というのは、TOEIC学習が続かない大きな理由です。
【大前提】習慣化がベストだけど・・・
ここまでモチベーションの話をしてきましたが、モチベーションは一時的な感情の高まりに過ぎないので、実はあまり長続きしません。
勉強はモチベーションに頼るよりも習慣化するのがベストです。
実際、世の中にも習慣化の方法をテーマにしたビジネス書などがたくさん出回っています。
ただ、あまり習慣化の方法ばかりに気を取られ、肝心の勉強がおろそかになってしまっては本末転倒。
いくらコツコツと続けなければならないとしても、目標にはできるだけ早く到達したいですよね。
であれば、ある程度はモチベーションに頼って勢いをつける必要もあるはずです。
まずは大前提として、このようなモチベーションと習慣化の関係を念頭に入れておいてください。
モチベーション低下を防ぐ方法
それでは、ここからモチベーション低下を防ぐ方法をご紹介いたします。
全部で10の方法がありますが、分かりやすいようにいくつかのパートに分けています。
「目標の設定」編
1、具体的な目標と期限を決める
最初の方法は具体的な目標と期限を決めるというものです。
例えば「半年以内にTOEICで450点をクリアする」のように数値化できる目標を設定しましょう。
TOEICなら目標スコアがあるので、数値化しやすいですよね。
ただ、ここで大事なのは、スコアだけではなく期限も決めるということ。
いつかクリアできればいいや、みたいな気持ちではいつまで経っても目標はクリアできません。
目標達成の期限を決めないと、日々やるべきことが定まらず、結果的に実力もつかないからです。
日々やるべきことを決めてコツコツ勉強を進めていくためにも、スコアと期限を含めた具体的な目標を立てるようにしましょう。
2、目標を細分化する
目標を細分化、つまり細かく分けるというのもモチベーション維持に役立ちます。
大きな山を登るのが大変に感じるのと同じように、多くの場合、最終的にクリアすべき目標というのは達成困難に思えてしまいます。
「こんな目標、本当に自分が達成できるかな」と不安になるのです。
そんな時は大きな目標を小さなステップに分けることで、前に進んでいることを実感しやすくなります。
山登りでいうと「まずはあの山小屋を目指そう」といった感じで、短期的に達成できそうなステップを設定して1つずつクリアしていきましょう。
たとえ小さくても、1つの目標をクリアすれば達成感が得られるので、モチベーションの低下を防ぐことができます。
「今月中にこのテキストを終わらせる」「今月はこの問題集」といった具合に進めていけば、気がついたらかなり進んでいた、という結果になるはずです。
「日々の記録」編
3、To-Doリストを活用する
目標を細分化していくと、1週間または1日といった短期的な計画も立てやすくなります。
その短期的な計画が目で見て分かるように、やるべき内容をTo-Doリストとしてまとめましょう。
To-Doリストは簡単な箇条書きで構いません。
やるべきことを全て挙げ、終わったら消していきます。
こうすることで、1つずつ前進していることが視覚的に捉えられるため、モチベーションを保ちやすくなります。
また、リストを見れば残りのタスクも分かるので、それらを終わらせるためのスケジュールも立てやすくなるという点もメリットです。
4、学習記録をつける
日々の学習内容や時間を記録することで、自分の努力を「見える化」できます。
英語の勉強は、すぐに成果が目に見えて分かるというわけではないので、自分の勉強がどれだけ進んだのかを記録するとモチベーション維持に役立ちます。
単なる記録だけだと単調になってしまうので、勉強した感想も書いていくとより効果的。
記録が増えていくことに加え、日々の気持ちの変化を見返すことで、勉強を続けてきたことの達成感が得られます。
「時間の使い方」編
5、学習のペース配分に気を付ける
勉強の進め方として、毎日少しずつ進めていくのか休日にまとめて進めるのかは人それぞれですが、どちらにしてもやるべき分量を見定めた上でペースを守って進めていきましょう。
ただ、個人的には毎日少しずつ解いていくことをオススメします。
なぜなら、TOEICの勉強はある程度の長期戦になりますが、早い段階でがむしゃらに進め過ぎると、途中でバテてしまい、最後までまで勉強が続かなくなるからです。
人間の脳は、できるだけリスクを回避するために普段と同じことを選びたがります。
逆にいうと、普段やらないことをやろうとする時はストレスを感じてしまうのです。
ですから、普段やらないことを休みの日にまとめて行うと、脳はストレスを感じてしまい、継続することが徐々に難しくなっていきます。
これが三日坊主の原因です。
そうならないために、少しずつでいいので毎日コツコツと続けていきましょう。
一日でやるべき分を終らせれば気分も良くなるので、それ以降も続けやすくなるはずです。
6、学習内容に応じて時間を使い分ける
これは、時間をかけてじっくり取り組むべき内容なのか、スキマ時間を使った方がいいか、ということです。
問題を解いたりテキストを読んだりするには、まとまった時間を使ってじっくり取り組む必要があります。
短時間で済ませようとすると中途半端にしか理解できず、結局何も身につかないからです。
一方、単語を覚えたりするのは、短い時間で集中して行う方が効率的です。
1つの単語の意味と使い方をチェックするのに時間はかからないので、スキマ時間を活用するようにしましょう。
(スキマ時間=電車やバスに乗っている時間、大きな用事の間にできた空き時間など、日常生活の中で生まれる細かい時間)
短い時間にサッと勉強するだけでも、かなりの力がつきますので、有効に活用してください。
7、まとまった時間を小分けにする
休日など、まとまった時間を勉強に使える時でも、あまりまとめて使わないようにしましょう。
まとまった時間をできるだけ小分けにして使います。
たとえば勉強に使える時間が3時間あるからといって、3時間ぶっ続けで勉強しようとしても、なかなか集中力は続きません。
もしこの時に、買い物や家事など他の用事があるなら、3時間の勉強時間を1時間ずつに分けて、その合間に他の用事を入れてみましょう。
そうすると、集中力が切れかかってきたタイミングで勉強から離れることができるので、疲れた頭をリフレッシュできますし、他の用事も済ませられます。
好きな音楽を聴いたりしながら用事に取り組み、勉強も用事も上手に進めてください。
同様に、仕事に行く前に1時間勉強する時間があるなら、自宅でまるまる1時間勉強するのではなく、自宅で30分、通勤途中のカフェで30分、などとしてみましょう。
続けて勉強する時間が短くなる分、集中力も切れにくくなります。
「目標を達成する環境」編
8、周囲に目標を公言する
基本的に、人間は自分に甘い生き物です。
目標を決めても、つい「今日はいいや」「明日から頑張ろう」と自分を甘やかしがち。
そんなことを繰り返すうちに、いつの間にかモチベーションも低下、ということになってしまいます。
この自分への甘さを封じるには、周りに監視役を置くのが効果的です。
家族や友人、同僚に目標を宣言することで、周囲からの監視にさらされることになるため、もう自分を甘やかすことはできません。
そのような人が近くにいなければ、ネットを活用しましょう。
SNSや日記ブログなどで学習状況を配信することで、他人からの目を意識できるようになり、モチベーション低下を防ぐことができます。
9、予約メールを活用する
「いつまでに何を終わらせる」という日々の目標をメールに書いて、それを自分宛てに予約送信するのも使えます。
目標として定めた期限を送信日時に設定しておくことで、その日時に過去の自分からのメールが届く仕組みです。
「自分で決めたことはやり遂げなければ!」という気持ちが働くので、メールが届く前に終わらせるモチベーションが上がります。
これも「4、学習記録をつける」の話と同じように、目標を立てた時点の気持ちを書いておくと、その時の思いがよみがえるので、さらに効果的です。
10、学習仲間を作る
よく言われることですが、人間を成長させるのは環境です。
周りにダラダラ過ごす人しかいない環境と、目標に向かって日々努力している人に囲まれた環境。
自分を成長させるためにどちらが適しているのかは明らかです。
自分と同じ目標を持っている人を学習仲間にして情報交換したり互いに励まし合ったりすればモチベーションは低下しにくくなります。
8で述べた「周囲に目標を公言する」というのは、あくまで目標を伝えて監視してもらうものですが、同じ目標を持っていれば、監視だけでなく仲間として一緒に進むことができます。
ネットで調べれば勉強会やオンラインコミュニティが見つかると思いますので、積極的に参加してモチベーションアップを図りましょう。
最後に
いかがでしたでしょうか。
冒頭にも書きましたが、英語力を身に着けてTOEICのスコアをアップさせるには、何よりも継続が大事です。
そのためのモチベーション維持も簡単ではありませんが、ここでご紹介した内容を参考にしていただき、コツコツと学習を継続させてください!
